
たまにどうでもいいことを書きたくなる。
いや待て。
いつもどうでもいいことしか書いていない・・・。
まぁいい。
先日、少々お高く止まっている銀座のアパレルショップに行ってきた。そこでジャケットなんぞを手に取り見ているとお高い店員が話しかけてきた。
そもそも銀座のアパレルショップなんてところは、二十代辺りの若い頃自分には簡単には足を踏み入れることができない聖地のようなところであり、入るのをためらい、それでも勇気を振り絞って足を踏み入れ、入れば入ったで店員に話しかけられないよう陳列棚の間を逃げ回り、話しかけられれば下を向き、「似合いますよ」と勧められれば全て買ってしまうといった具合の負け戦しかできない場所だった。
けれどそれも今となっては昔の話、最近では何着か気ままに試着し、それによってひと手間かけさせてしまった店員に対しても「買いますか?」と問われればその目をただ真っ直ぐに見ながら「NO」と言えるくらいには適度に程よく図々しい中年に育っている。
そんなわけで先日、そんなジャケットを漁っている中年である自分にお高い店員が話しかけてきた。
店員は五十歳を過ぎているだろうベテランで、白髪を無造作に流しながらワックスでテカらせ、年齢に合わせた渋さを濃いめの顔にたくわえ、オサレなジャケットをデニムに合わせ、フォーマルの中に遊び心を見せつつ、『ダンディー』という名のなにかを全身の毛穴から絶えず放出している「どうだい?今でも俺イケメンだろ?」的なおっさんだった。
昔はさぞかしおモテになられたんでしょうね、と言ってあげたくなった。
けれど決して言わない、たぶん調子に乗るだろうから。
そんなタイプのおっさんだった。
正直好きではないタイプだ。
若い頃の自分であれば、あまりのダンディーさにその場から逃げ出すか、もしくは動けず失禁していたかもしれない。
けれどこの日は彼の吐き出すダンディーを巧みに避けながら、そして床の至るところに落ちたダンディーを踏まないようステップを踏むようによけながら、それらの落ちダンディーたちを横目で確認しながら商品の品定めを続けてみせた。
いやそもそも『ダンディー』ってなに?って疑問が出てくるだろうから書いておくと、それは体内で生成されたのちに毛穴から発せられ、当たれば相手にダメージを与え、そうでなければ床に落ちて静かに溶けてゆく、そんな京都で伝統的に作られている何かのようなものだと思っている。
つまりなんなんのかははっきりわからない。
たぶん現在の科学ではまだ解明できないんだろう。
ダンディーとはつまりそういうものなのだ。
そんなこちらの気持ちを知りもしないダンディー使いの五十過ぎのダンディー店員が、やっぱり十分に熟した中年である自分の横に従者のように付き従っている。
邪魔だ・・・。
どこかに行ってほしい。
けれどそんなことは言えやしないので、差し障りのない程度で「この服の素材ってなんですかね?」だとか「出張用で軽めのシワになりにくいジャケットってありますかね?」などといった質問を投げかけ、そして彼からの回答に耳を傾けていた。
そんな何気ないやりとりを適当に何回か繰り返してその場を乗り切るつもりだった。
ところがこちらの質問に対しての彼の回答を聞いていて気づいてしまった。
ああ・・・
この人・・・
すこぶるバカだ。
回答が的を射ていないし話が下手過ぎる。
まったくもってこちらの欲する回答が来ない。
凝っている箇所をなぜか押してくれないマッサージ師のようで気持ちが悪い。
もっと言うなら、こいつは外見だけで生きてきたただの底抜けバカ野郎だとも思った。
いや、ちょっとひどいことを書きすぎた。
一応謝っておこう。
すいません。
とはいえ、どうりで簡単にダンディーを避けられた訳だ。
プロのダンディーが発するダンディーだったら速すぎて避ける暇などない。
今頃床に這いつくばって頬を踏みつけられながら片目で彼を見上げていたことだろう。
危なかった。
そう思ったら今の状況がなんだか嬉しくなった。
なんならリトルダンスを踊りたくなるほど嬉しくなった。
つまりは小躍りしたいくらいに嬉しくなった。
なにしろプロダンディーではないとはいえダンディーに負けやしなかったんだから。
そして全てのイケメンやダンディーは俺たちの敵なんだから。
これまで恐れていた銀座という魔界に幾筋かの光が差したようにすら思えた。
そんな状況に満足した自分はさらなる余裕を体内に蓄え、五十過ぎのベテランダンディーが勧めてきた派手なジャケットに対し、静かに、そしてはっきりと『NO』という言葉を突きつけ静かに店を後にしたのだった。
そんなどうでもいい話。
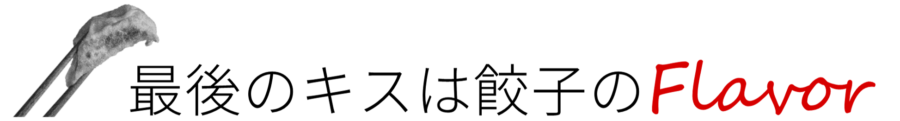














-150x150.jpeg)





